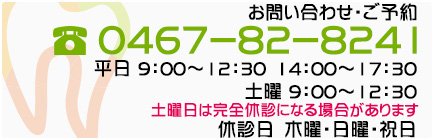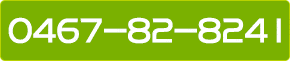アトム歯科医院 院長:菅 清剛
昭和20年(1945年)8月18日生まれ
秋田県出身
1971年 神奈川歯科大学 第1期卒業
1975年 アトム歯科開業
現在に至る
茅ヶ崎で開院して、48年になります。
歯周病やその予防を中心に、歯槽膿漏、入れ歯、義歯、虫歯などの治療を行っております。
私の趣味
「歯科医の趣味」という題で何か書けといわれて、困ってしまい、趣味とはどういうことを意味するのか辞書を引いてみた。
大言海にいわく、
①オモムキ、オモシロミ、アヂハヒ、興味、風韻
②智的思考
③美を弁別スル能力
とある。
これからすると、自分は無趣味だから書くことがないというと、この人生になんの興味あることもないということになり、どこかで生き方をまちがえたのを自ら認めることになりそうである。
しかし、あれこれやっていても、あるいは何かにオモシロミを感じていても、本当に趣味と言えるかとなると、みな考え込んでしまう程度のものなので、不本意ながら、やっぱり自分は無趣味といわざるを得ないのかなと思ったりもするのである。
そうはいっても、なにか趣味について書かねばならないはめになっていることもあり、あまり固く考えないことにして、ひとつだけ挙げるとすると何を基準とすれば良いのだろうと、いろいろ考えてたどりついたところは、「その間、時間を忘れてしまうもの、自分を忘れてしまうもの」である。
これをもとにすると私の趣味が、自分でも驚き、そして、思わず一人で笑ってしまったのは、それが「仕事」だったからである。
仕事が趣味というのは父の時代の話で、今どき流行らないというより、ほとんど恥ずかしいことのように考えていた。
ここで父の時代といったのは、父の残してくれた色紙が私の机の上にかけてあり、「天職と信ずる仕事に、生涯一貫して変わらぬ情熱と信念を持ち得ることは人生最大の幸なり」と書かれているためである。
趣味と仕事が同じという事から父の色紙を思い出したぐらいであるから、天職とは趣味が仕事となった時としてもそんなに外れていないと思う。
歴史に名を遺した人たちの多くが、ある意味では趣味が即、仕事であり人生であったように私には思え、そこから湧いてくるエネルギーでないと人に影響を及ぼすような力(芸術にしても学問にしても)にはならないことを彼らは教えてくれているような気がする。
最近、奥村土牛が101歳で亡くなったが、補聴器・総義歯を最後まで使わなかったという話に感銘を受けた。
凡人であれば、まず間違いなくボケているような肉体的条件のなか「何歳になっても達成はありえない」と絵画に対する情熱を最後まで持ち続けたのは、このエネルギーの存在があったからではないだろうか。
そのエネルギーが耳や歯を失っても、画を書くために必要な眼を最後まで守ったのだと思う。
食物を咀嚼することは、身体そのものをリフレッシュする作用があり、咀嚼できないと生命力が湧いてこないといわれ、このことは真実と思うが、その前に人間が心底、生きる喜びを持っていることが、生命力の湧いてくる大前提になり、それがあれば人間はほとんどのことをクリアしてしまうし、奇蹟さえ起こしてしまうようだ。
ここらへんで、他人の口腔を年中のぞいているような、一般的には敬遠される歯科医療のどこに趣味となるほどの魅力があるのかを述べなくてはならないだろう。
しかし、これは歯科医師にしかわからないものであり、しかも、歯科医師に対しても、ことばで説明できるものではないようで、無理にそうしようとすると非常に陳腐なものになりそうである。
ただ、年齢と共に面白さが変わってくるという事とはいえ、最近は、次のことばに刺激を受けている。
「私たちは自分自身を知らない。私たちは真実や、本の中に書いてあることはたくさん知っているが、物を介さずに、自分自身の力だけで知ったり、自分で直接体験することがない」
このことばを歯科治療に置き換えてみるとどうだろうか。
成書のいっていること、あるいは。講演会の知識で一杯で、これらに振り廻されて、自分で知るよろこび、自分で直接体験するよろこびを忘れているような気がする。
ともあれ、すぐに仕事に結び付けてしまう自分は、趣味が仕事というより、仕事人間と言うのが一番適切のようだ。